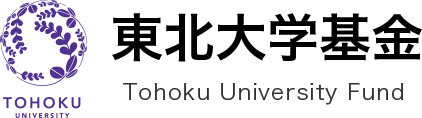寄附者Interview
Interview_004
齊藤 宏様・和子様ご夫妻 さん
工学部卒(宏様)・薬学部卒(和子様)
「寄附ができて嬉しい」と共に想う
齊藤 宏様・和子様からは、それぞれのお名前でずっとご寄附をいただいてきましたが、2022年3月にご夫婦連名で非常に大きなご支援をいただきました。ともにご卒業生である齊藤ご夫婦がどうして連名での寄附に至ったのか、お話をお聞きしました。
ご寄附者プロフィール
齊藤 宏様(株式会社キーペックス代表取締役会長):
東京都出身。文京高等学校から数年のインターバルを挟み、1958年に東北大学工学部に進学。漕艇部に入部し1年生から始めたボート競技のエイト(*)で整調を務める。この年のエイトクルーは指導者にも恵まれたほか極めて団結力や競技への意識が高く、当時国内で初めて6分を切る驚異的なタイムを叩き出し、東北大学のエイトチームが1960年ローマオリンピックに日本代表として出場。オリンピック本選では結果を残せなかったが、オリンピック出場経験は後の人生の大きな支えとなる。
1962年工学部卒業後、砂鉄関連企業に就職し青森県下北半島で鉱脈の探索に従事。その後、親が経営する倉庫業に従事しつつも更なる挑戦のために1984年隅田倉庫運輸株式会社を千葉市に設立し独立。その後1992年に社名を株式会社キーペックスに変更し、以降、「倉庫×イノベーション」を体現し続けている。
和子氏とは1965年に結婚し、2男1女に恵まれる。
(*)エイト競技:この競技は漕ぎ手に指示を出すコックスと8人の漕ぎ手の計9名で構成される。この9人が一体となったときに初めて爆発的な推進力が生まれる。
齊藤 和子様:
宮城県仙台市出身。宮城県第一女子高等学校から1959年に東北大学薬学部に進学。仙台市北七番丁が実家なため幼少のころから東北大学が身近な存在。大学に行くなら当然、東北大学に行くものと思い薬学部に進学。1963年卒業後は東北大学の化学工学専攻に就職。大学の友人で「ボート」が大好きな人が居て、その友人に誘われて漕艇部と接触するようになった。宏氏とは卒業間際に知己となったが、その後、縁があり結婚。結婚後は宏氏の仕事を手伝いつつも、基本的には専業主婦として宏氏、家族を支える。「食は全ての根源」との思いから家族への食事には人一倍気を遣う。大根も人参も皮は剥かない。
大学生活~その後の人生の土台
宏氏:
高校卒業後、最初は船乗りになりたくて商船大学を目指していましたが、ご縁が無く連敗。何年か過ごしているうちに高校の校長先生をしていた叔父に東北大学を勧められました。一生懸命勉強して何とか工学部に入学。東北大学漕艇部は、旧制二高から続く非常に伝統のある部活で、あと船も好きだったので入部しました。

ただ、朝4:30起床、7:00朝食、8:00登校、大学から戻ってきたら、16:00出艇、19:00夕食、21:00就寝と、毎日本当にきつくてきつくて何度も逃げ出そうと思ったのですが、当時の部員がエイトを漕げるちょうど9人しか居なかったので、辞めるわけにはいかなかったんです。自分だけ逃げるわけにはいかないと思いました。入学当初は全然体力が無く懸垂も1回も出来なかったのですが、半年経ったころには30回ぐらい出来るようになっていました。
体力面だけでは無く、当時の監督である堀内浩太郎さんは、とにかく部員の頭を使わせるように仕向けてきました。8ミリフィルムで我々の漕いでいる練習中の姿を撮影して、夜に合宿所で監督含めてメンバーでそれを見るのですが、監督自身はあれやこれやと細かくは仰らない。何が駄目でどこが良くないかを、我々自身で気付けるようにしてくれていたのだと思います。
そういった自分に気づかせる指導者としての姿勢は、私自身が経営者となってスタッフに考えてもらいたいとき、本当に役に立っていると思います。
そういった頭も体も限界まで使った練習を重ねているうちに、ある日突然、9人の息がぴったりとあって6分を切れるようになったんです。しかも早く漕げたときはそんなに疲れない。それで1960年5月の全日本選手権に優勝して、ローマオリンピックへの出場が決まったんです。オリンピックへの出場に際しては、漕艇部長の医学部・武藤教授はもちろんのこと東北大学のたくさんの先生に支援をしてもらいました。こういった支援も御恩だと思っています。
また、当時のボートは本当に世間の注目を集めていて、出場を決めた5月以降、オリンピック本選の9月まで連日全国紙に掲載されたち朝日グラフ、サンデー毎日などの取材がずっと入っていました。
1960年5月 ローマオリンピック代表選考予選準決勝 5分59秒6という当時の日本記録をマークした。

1960年ローマオリンピッククルー 監督:堀内浩太郎、コーチ:冨永、香川、
舵手:三沢博之/整調:齊藤宏/7番:佐藤哲夫/6番:斎弘教/5番:田崎洋佑/4番:斎藤直/3番:廣瀬鉄蔵/2番:田村滋美/1番:千葉建郎

和子氏:
私は薬学部に進学して、薬草のことを学んでいました。学生時代の勉強はとても面白くて良かったのですが、教授始め先生方ともっと身近にお話をしたかったなぁ、という想いはずっと残っています。
宏さんは、1984年に独立して自分の会社を起こしたんですが、その前ぐらいからずっと楽しくなさそうだな、と思っていました。安定的な収入が無くなるかもしれないと独立の相談を受けたときも「家族は、野草でも何でも食べて生きていけるから心配しないで」と言いました。こんなことを言えたのも、薬草のことを学んだお陰だと思います。

宏氏:
妻がこのように言ってくれて後押ししてくれたのは、本当に有難かったです。もっとも、創設期メンバーで何とか頑張って早いうちに仕事を獲ってきて、家族に草を食べさせることは無かったのですが(笑)。
漕艇部でのハードな練習の日々だけでは無くて、研究室の先生方との関りも本当に有難いものだと記憶に残っています。私の恩師は工学部の鈴木廉三九教授で鈴木研究室のイベントで今でも深く心に残っているのは、福島県の吾妻山でのキャンプです。その時代はおおらかでしたから、当日の朝に鈴木教授から「よし、今日はキャンプに行こう」との掛け声で授業そっちのけでみんなでキャンプに出掛けました。焚火を囲みながら吾妻山の星空を見ながら、先生方が持ってきてくれたウイスキーなんかを飲みながら色んな話をするのですが、教授も含めた先生方との距離が本当に縮まったと思えた瞬間でした。若い時に色んな人たちの話をお聞きするのは良いことです。結局、鈴木教授には私たちの仲人も務めていただきました。

受けた恩を未来に繋ぐ-自身の想いを貫く
宏氏:
私も妻も東北大学から多くのものをいただけたと思っているので、いつか寄附はしたいな、とずっと思っていました。自分たちに何かあった際に相続税で持って行かれるよりも東北大学に寄附して、御恩返しと学生のために役立ててもらえると良いと考えました。

和子氏:
東北大学は個性的な人が多いのですが、一方で何かやるとなったら部局の壁を超えて非常に協力的でみんなで一丸となる大学だと思っています。そんな東北大学が大好きでずっと寄附したいとは思っていました。宏さんも私も無駄遣いはしないし贅沢も好きじゃないので。
今回、夫婦連名で寄附したのは宏さんのアイディアなのですが、事前に特に相談は無かったです。独立して会社を経営している人なので家庭内でもワンマンなところはありますが、連名にしてくれたのは、何も言わなくても私の東北大学への想いを知ってくれていたんだな、と凄く嬉しく思いました。
宏さんもだと思いますが、「寄附ができてうれしい!」という気持ちにもなりました。
宏氏:
これからの東北大学に期待することですが、学生と教員の壁をもっと薄くしてもらって、距離が縮まるようになって欲しいです。学生はみんな違うものを持って生まれてきているので、それを発揮できて「どんなことがあっても生きていける」というような実感を持ってもらえると良いかと。大学は高校時代とは違って、すごく良い時期だし、大事な時期だと思います。学生をお客さんだと思って、真に学生に必要なことを提供できると学生は物凄く恩義に感じるようになると思います。
恩義を受けて大学のことを想う学生を1人でも多く育てていく、そんな大学になっていって欲しいです。
編集後記
お話を聞いていて、本当に東北大学のことへの想いを感じさせていただいたと同時に、ご夫婦の信頼関係にも感銘を受けました。宏様からのお言葉にもあるように、学生が恩義に感じるぐらいのことを提供できる大学になっていくことは、今後の東北大学の在り方にも大変重要なことだと思いました。
(2025年1月インタビュー実施。株式会社キーペックスにて。
インタビュワー・文責:基金・校友事業室 小玉)
参考リンク:前回のインタビュー(https://www.kikin.tohoku.ac.jp/donors-voice/001)
2018年3月桜の植樹(https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2018/03/news20180330-02.html)